はじめに
※この記事は診断を確定するものではありません。
※異変や不安がある場合は、一刻も早い受診をお願いします。
あくまでも個人&個犬の実体験です。
「シニア犬の子宮蓄膿症とその対処・治療」について、
実際に犬と私が経験したことなので、
同じような不安のある方に参考になればいいなと思い記事にします。
重ねてのお願いになりますが、
「調子が悪そうだけどどうしたのかな?」
「もしかして…?」
と思い当たる様子がある場合は、
当記事を含め、ネットの情報を材料に素人判断であれこれ悩む前に一刻も早い受診をお願いします。
みんなが大事な家族を守れますように。
今回のケース

当該犬のプロフィール
- メス
- 柴犬
- 10~11歳くらい(保護犬のため正確にわかりません)
- おそらく出産経験あり
- 治療中の病気はなし
うちに来て10年ほど。
引き取ったときの正確な年齢がわからないのでおよその年齢。
さらに、
持病(治療歴や罹患歴)の有無、出産経験の有無も不明です。
保護当時の簡易検査では特に異常なし。
たぶん出産歴があると思われます。
気になった症状
- 多飲多尿
- 食欲不振
- 元気がない
- 生理終了後もわずかに出血が続く
- 陰部を気にする
- おなかのハリ
9月の半ばごろに秋の生理(発情期)が終わりましたが、
10月2週目の時点でもわずかな出血(黒い血)が続きました。
とにかく水をよく飲み、
飲みすぎて吐いたり、
たくさん飲んでいる分トイレの回数・量が増えていました。
※食欲に関してはもともとムラがある子。
10月になってぐっと気温も下がり、
気候が変化したタイミングだったので
はじめは季節の変わり目不調を疑いました。
経過①
かかりつけ医を受診(1回目)
季節の変わり目不調を疑い受診。
微熱があったので、
抗生物質の注射と、食欲増進の注射で様子見。
翌日も注射に来るようにとの指示。
かかりつけ医を受診(2回目)
前日同様、抗生物質の注射と食欲増進の注射。
受診前よりは体を起こしている時間も長く、
食事も少しだけ摂るようになった。
翌日が休診のため、
心配であれば休み明けに再度受診をとの指示。
経過② セカンドオピニオン

かかりつけ医を2回受診した後も大きな改善が見られなかったので、
セカンドオピニオンとして違う病院でも診てもらうことにしました。
結果論にはなりますが、
今回はこのセカンドオピニオンが早期治療につながりました。
新規の病院を受診
身の回りの犬飼い・猫飼いさんにかかりつけ医を聞いて回り、
受診している人が数名いた病院に行くことに。
いまは口コミもネットで見ることができますが、
実際に通院している人からの情報はかなり参考になります。
身の回りに動物飼いさんがいるなら情報収集を。
『子宮蓄膿症』の診断
現在確認できる症状と、血液検査の結果から
『子宮蓄膿症』の可能性が高いとの結果になりました。
子宮蓄膿症は、
シニア期の未避妊のメスによくみられ、
子宮内部で細菌感染がおこることで膿が溜まり、
命にかかわる緊急性の高い病気です。
治療が遅れると、
他の臓器に負担がかかることで急性腎不全や腹膜炎などになる可能性も高く、
膿が溜まった子宮がお腹の中で破裂してしまうことで
ショック状態に陥るなど危険です。
なるべく早く適切な処置を行わないと、
手遅れになってしまいます。
治療法① 外科的処置(手術)
提示された選択肢のひとつが外科的手術。
いわゆる
「避妊手術」とすることは同じで、子宮及び卵巣の全摘出です。
メリット
- 病気の原因を取り除くので、「子宮蓄膿症」は完治する
- 発情期の際の負担が犬も人も軽くなる
デメリット
- 全身麻酔など、手術自体にリスクがある
- 基礎疾患の有無や年齢による不安事項がある
治療法② 内科的処置
もうひとつの選択肢が内科的処置。
抗生物質の投与と、
子宮を収縮させる薬を使って膿を排出して、炎症を抑える方法です。
メリット
- 全身麻酔や開腹など、外科的手術よりはリスクを抑えられる
デメリット
- 治療の期間がかかる
- 投薬の効果が出るかは個体差がある
- 発情期を迎える度に、子宮蓄膿症の再発・悪化のリスクがある
選んだ治療方法

先に紹介した治療方法とメリット・デメリットを勘案して
私たちが選んだのは外科的処置です。
最終的に手術に踏み切った理由は、
- ほかの疾患と違い、病巣を取り除くことが可能。手術がうまくいけば子宮蓄膿症自体は完治の見込みが高い
- 内科的処置がうまくいったとしても、発情周期ごとに子宮蓄膿症が再発する可能性があり、場合によっては悪化の可能性がある
- そうなった場合、現状(今回)よりコンディションがいいとは限らず、治療の幅が狭まってしまうかもしれない
もちろん、
- シニア犬であること
- 保護犬であるため基礎疾患や出産経験の有無などが不明
- 全身麻酔のリスクや術中死
- 術後の合併症
- 経過不良 など
リスクはとても怖かったです。
このリスクは、
犬種や年齢など個体差はあるものの
すべてのわんこが負っています。
単身者であれば自分自身の決断ですが、
家族で暮らしている場合は意見が割れることもあるでしょう。
実際私たちの中にも
「手術は怖いから内科処置にしよう…」という意見が出ました。
どちらが正解・不正解という話ではないので、
それぞれが納得いくまで話し合いが必要です。
治療の結果次第では
「あの時ああしていればこんなことには…」と争いを生む可能性も。
最愛の家族を前に、
そんなことで喧嘩したくないですよね。
当時の状況から、
手術をするなら緊急で翌日に予定を入れるとのことで、
診断を受けたその日にどちらにするか決めなければいけませんでした。
最後はみんな納得した上で手術をお願いしました。
でも、
本当に本当に怖かった。
このまま会えなくなるんじゃないかと、
当日の朝は待合室でずっと抱きしめていました。
病院から連絡があるかもしれないと思うと、
気持ちも落ち着きませんでした。
結果・経過
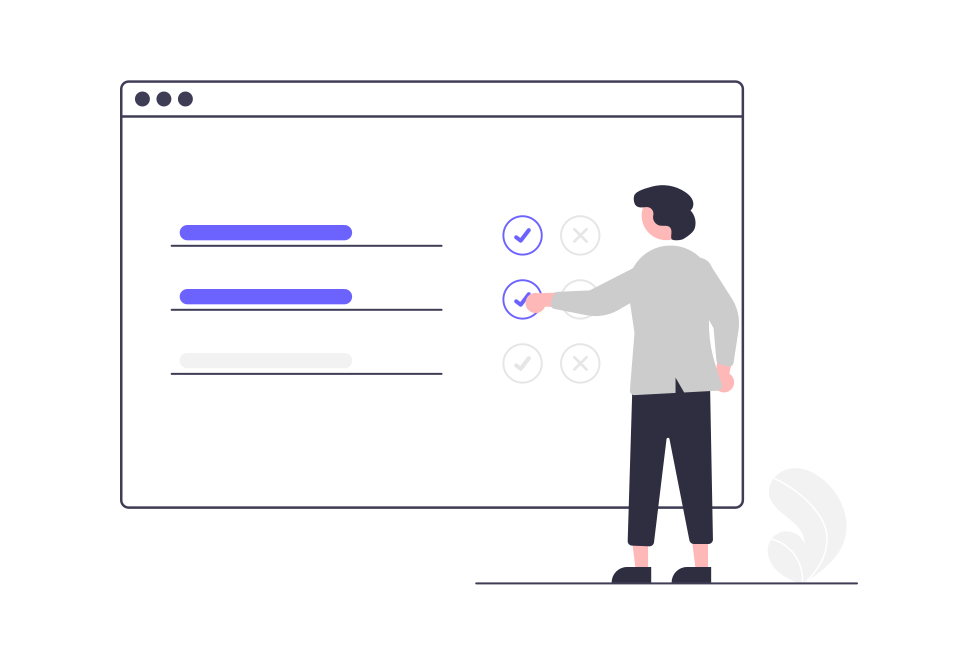
手術は無事に成功。
術後の経過も悪くないようで、
血液検査の炎症や白血球の数値も基準値内まで下がり安定しています。
術後1週間ほどは入院の予定でしたが、
経過が安定していて、
いつもと違う環境で緊張したのか
思うように食事を摂らなかったこともあり5日目に退院。
自宅に戻ってきてからは
抜糸までの1週間ほど抗生物質を飲ませることになりました。
まだ経過観察は必要ですが、
ひとまずよく頑張ってくれました(´;ω;`)
大丈夫だと信じてはいても、よくない結果は想像しちゃいますよね…。
元気になって帰ってきてくれて本当に良かった。
先生をはじめ、病院スタッフのみなさまに感謝です。
子宮蓄膿症の手術費用
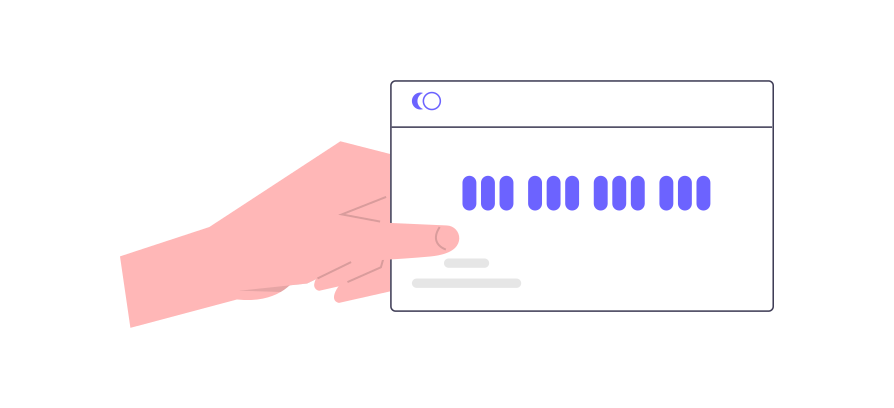
気になる一連の費用ですが、
トータルで13万円弱かかりました。
- 初診費用(血液検査など含む)…約1万5千円
- 手術&入院費(4泊5日)…約12万円
検査の数や入院日数などで差がつくと思いますが、
10~15万円くらいかかると言われていたので
このあたりがひとつの相場のようです。
ちなみに今回は外科治療でしたが、
内科的治療を選んだ場合でも、
治療開始~一旦終了までのトータルコストは大差ないとのこと。
突発的な出費なので家計にとってはちょっと痛手。
不安な場合は、
毎月の積立やペット保険などに加入しておくのも
備えとしては有効かもしれません。
今回は保険未加入だったので
すべて自費診療になりました。
アニコムなどが有名ですが、
いまはアマゾンでもペット保険の取り扱いがあります(※新規加入は8歳まで)。
なるべく若いうちに加入しておくのがオススメです。
動物病院のセカンドオピニオンについて

ペットと暮らしている方なら
おそらく「かかりつけ医」があるはず。
私たちにもかかりつけ医があって、
ふだんはそちらにお世話になっていますよね。
「セカンドオピニオン」と聞くと、
いつもの先生や病院を信用していないような印象も。
ほかの病院にかかったこともなんだか言いにくいですよね…。
ただ、
同じような症状が続くとか、
治療の効果が思わしくないなど
気になることがあれば
迷わずセカンドオピニオンをおすすめします。
実際に違う病院にかかってみて、
- かかりつけ医では見つけられなかった症状がわかる
- かかりつけ医の設備的にできない検査ができる場合もある など
メリットが大きかったです。
日ごろから診てもらうことも大切ですが、
「(季節の変わり目や年齢など)いつもの不調かな?様子を見ましょう」
で終わっているかもしれないので、
新しい視点を取り入れることは悪いことじゃないです。
実際、
今回は様子を見る期間が伸びていたら、
手遅れになっていたはず。
自宅からの距離や休診日などを踏まえて、
いつでも病院にかかれる状態を作っておくことが大事だなと痛感しました。
これまでのかかりつけ医には
今まで通りお世話になる部分もあると思いますし、
特に気まずくなったりはしていません。
「動物たちが助かるのが一番いいこと!」と言ってくれる先生です。
新しい病院の先生も大変親切な方だったので、
心強い味方が増えました!
おわりに
- 少しでも普段と違う様子に気が付いたらすぐに受診する
- なんとなく様子を見たり、素人がネットの情報で勝手に判断しない(飼い主もどんどん不安になる一方)
- プロに診てもらって状況を固めてひとつずつ解決していく
- 治療方針の話し合いはきちんとする(家族や先生)
- 未避妊の場合は避妊手術の検討を
ネットの情報を鵜吞みにしないことが前提。
その一方で、
自分で調べて
「子宮蓄膿症かもしれない」とある程度検討をつけていたことは、
診断にひるまず、
提示された選択肢の中から治療方法を選ぶ手助けにもなりました。
そういうメリットもあると思います。
ただ、
だいたいどれも最悪の結果が書いてあったので、
勝手に不安に突き進んでいくくらいなら早く受診しましょう!
かけがえのない家族を助けられるのは飼い主だけです。
夏から秋に移ろい、
発情期を迎える子たちもいる頃かと思います。
私たちの家族が、
どうか少しでも長く元気で健康に過ごせますようにと願っています。


